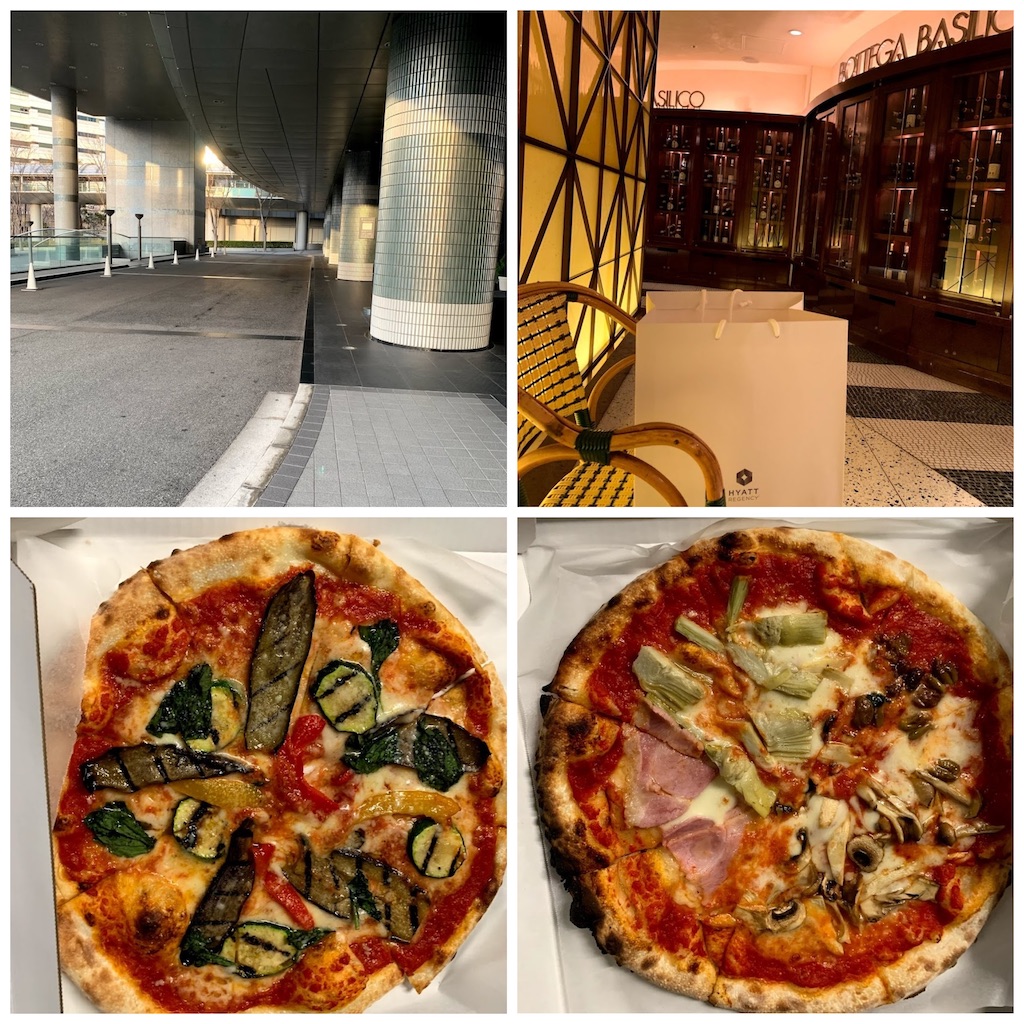深夜、階下から声が聞こえて目が覚めた。
夜食の後、二男が家内のヘッドマッサージを受け、二人であれこれ話しているのだった。
そんな話し声がまるで休日の雨音のように心を落ち着かせる。
安らかな眠りの世界へと引き返しつつ、いつの日か孤独だったことを思い出した。
遠い記憶の断片を手繰り寄せ、そこに残存する微かな感触を探ってみた。
胸の奥に潜んでいたのは痛みだろうか。
奥の奥であるから、手を当ててもその痛みを和らげることができない。
そんなもどかしい感覚につきまとわれるのが孤独であった。
いま、孤独と縁遠くなって久しい。
家に帰れば家内がいて、常時その独演会を楽しめる。
息子らともしょっちゅう連絡を取り合っている。
先日はお揃いの服を買って着て、二男と肩を組んで写真を撮った。
それでその写真を長男に送って、ついでに長男の分のお揃いも送った。
このように、わたしはいつだって家族と一緒に過ごしている。
職場もかつてはわたし独りだった。
それがいまでは、若く頼もしい助さん格さんがいて、わたしは精神的にとてもほぐれて楽になった。
対比によって絶対的な価値が明瞭となる。
病気になったときなど顕著。
痛風で足が痛いとき、普通に歩けることの喜びを痛感できる。
そのようなことである。
例えばコロナにかかると息が苦しくなるという。
だから、もし万一そうなれば、単に息をするだけの価値の絶大を思い知ることになるだろう。
他の何かに代え難い。
そんな絶対的とも言える価値に、実はわたしたちは取り巻かれている。
が、愚かしいことに、ついうっかりわたしたちはそんな価値を見過ごして、他のチンケな何かに気を奪われてしまう。
だから大事なものを見失わぬよう、気がつく度、大喜びしてその価値の絶大を胸に刻印する必要があるだろう。
そんなことを考えつつ、わたしは大いに喜びベッドに深々身を沈めた。