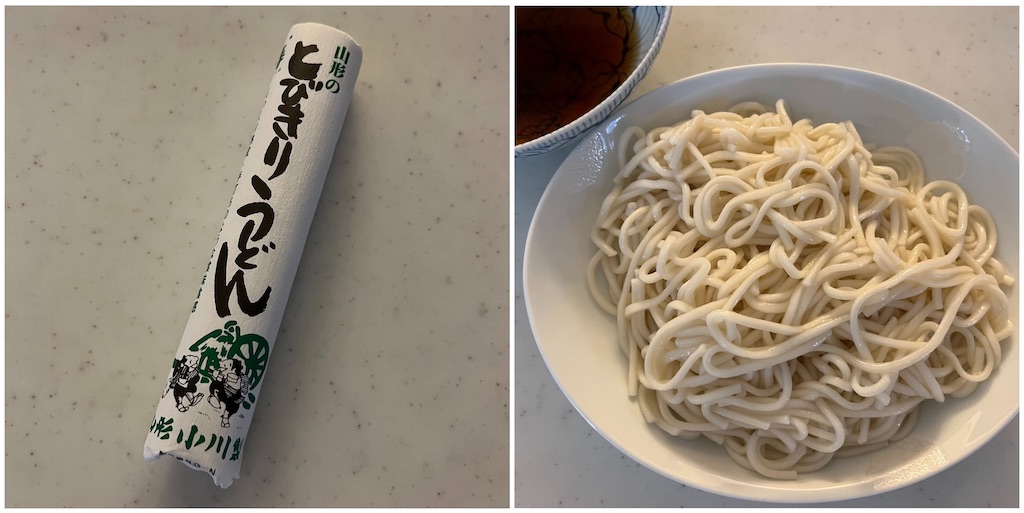イルカショーの会場は屋外にあった。
間近にある海から間断なく風が吹いて涼しい。
しかし、直射で陽の光を受けるとかなり堪えた。
だから大勢の人が日陰を選んで集まった。
水族館であるからほとんどが子連れで、アジアNo.1であるから様々な場所から観光客が押し寄せていた。
ざっとみて日本人より韓国や台湾の方々の方が多いとの印象を受けた。
しかし、やることはみな同じだった。
イルカがよく見えるよう、母は子を抱きかかえ、父は子を肩車し、おじいちゃんは孫をおんぶしてといったように各自各様のスタイルを取りつつも、「子どもため」という点で完全に一致していた。
もちろん礼節を弁えた東アジアの民である。
後方の視野を塞がぬよう前屈みとなるなどしていたから、ただでさえたいへんな姿勢が重労働の域へと達しているのは明らかだった。
それでもみな一様に各自の母語で「ほら、イルカだよ」と子に囁いて、とても優しい。
子どもたちは笑顔満面。
立体感と躍動感にあふれるバンドウイルカの迫力ある動きを夢中になって目で追っていた。
子どものそんな様子を目にするだけで親は報われる。
だからしんどい姿勢をとっていても、親の表情はいたって柔和で穏やかなのだった。
なるほど、これがヒト。
このようにしてヒトは世界のあちこちで子を連綿と育ててきたのだった。
だからそんな光景を目にして、わたしたち夫婦の会話は子育ての記憶を巡ることになった。
ヒトとしてわたしたちも例外ではなく、負荷などものともせず喜びをもって子らを育ててきた。
家内は息子たちを自転車の前と後ろにのせプール教室へと連れ、わたしは息子たちを自転車の前と後ろにのせ銭湯へと連れ一緒にフルーツ牛乳を飲んだ。
そして少し大きくなってからはクルマにのせラグビーの練習場へと送り出し、深夜となる時刻、連日のように塾まで迎えに行った。
家内は朝昼晩と料理を作り、わたしは昼夜を問わず平日も休日も問わず仕事に明け暮れた。
しみじみとした気持ちになって、夫婦で思うことは同じだった。
また近々、彼らの住む東京を訪れよう。
彼らを肩車したり抱っこする季節は遠く過ぎ去ったが、なにかしら「ほらイルカだよ」と囁くような話の種はまだまだ尽きていない。
夏が終わり秋の気配が漂う頃、東京の魅力がいっそう際立つ。
ヒトとして、この夫婦の役割に終わりが来るのは当分まだ先のことだろう。